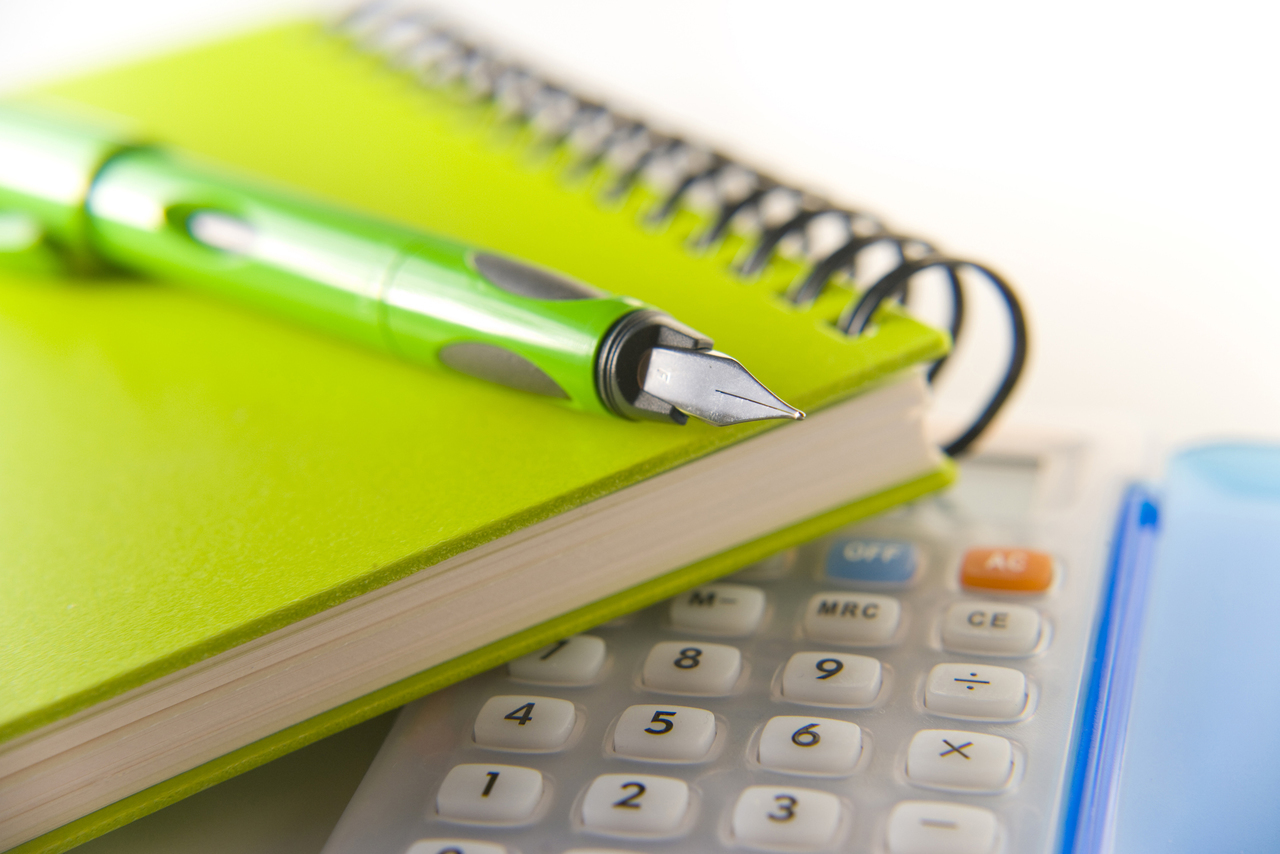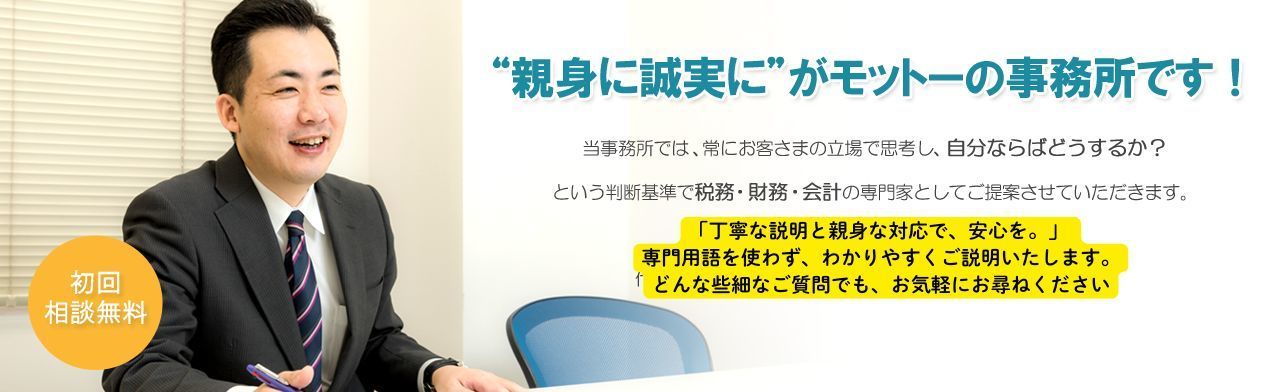税理士と社労士のダブルライセンス事務所
小川会計事務所・小川労務事務所
〒162-0066 東京都新宿区市谷台町16-6 16ビル2階
受付時間 | 10:00~17:00 |
|---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
|---|
役員報酬のルールと決め方のポイント
役員報酬のルールは厳しい

経費の中で大きな割合を占めてくるのが「人件費」です。特に会社経営者にとって自分の給料「役員報酬」の額をいくらにしたら良いかというのは頭を悩ませるところです。
会社の為に自分の給料を少なくしておいたら、会社で思った以上に利益が出てしまい法人税が高くなってしまった・・・
自分の給料を高く設定しすぎて、会社が赤字になってしまった・・・・
こうしたことから「儲かったら役員報酬を高く、儲からなかったら役員報酬を低くしよう」と考える方もいると思います。
しかし、役員報酬が経費(損金)として認められる為には、厳格なルールがあります。
経費(損金)に算入される役員報酬は以下の3つに限られます。
- 定期同額給与
- 事前確定届出給与
- 利益連動給与
定期同額給与

定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごとの給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
ここで重要なのが、給与改定の時期です。
役員報酬の額を改定することができるのは、
原則として期首から3ヶ月以内の時期に限られています。
それ以外の時期に改定した場合には、差額部分が経費(損金)にはならず、税務調整の対象となります。
つまり、事業年度開始から3ヶ月以内に一年分の役員報酬の金額を決定しなければならず、決定した後は一年間変更することが出来ないということです。
役員報酬の金額の決定については、慎重に行う必要があります。
事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、届出期限までに税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出しているものをいいます。
届出期限は原則、次の1.又は2.のうちいづれか早い日となります
- 1株主総会等の決議をした日から1ヶ月を経過する日
- 2事業年度開始の日から4ヶ月を経過する日
事前確定届出給与は、事前に届け出ている金額と少しでも違う金額を支給してしまうと全額が経費(損金)として認められなくなってしまいます。
相当精密な事業予測が必要となりますので、使い勝手がいいものでなく、経営に柔軟性を求められる中小企業には不向きと考えます。
利益連動給与
同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(益に関する指標を基礎として算定される給与)です。 算定方法が、有価証券報告書に記載されるものとして客観的なものでないといけません。 ですので、中小企業には不向きなものと考えます。
役員報酬の決め方
「役員報酬の額をどれぐらいに設定すれば良いの?」 お客様からこのような御相談をいただくことがあります。 資金繰り・事業損益の見通し・社会保険の負担等を含めて検討すべき問題ですが、 単純に「節税」といった観点から役員報酬の額の決定方法を検討してみましょう。
( 所得税率 + 住民税率 ) < 法人税等率
ポイントとなるのは上記の算式です。 それでは、法人税等率は何%位なのでしょうか。
法人税等の税率(数値は目安となるものです)
| 年間所得400万円まで | ||
|---|---|---|
| 税目 | 所得に対する税率 | 参考 |
| 法人税 | 15.0% |
|
| 復興特別法人税 | 1.5% | 15.0% × 10% |
| 事業税 | 2.7% | |
| 地方法人特別税 | 2.19% | 2.7% × 81% |
| 法人住民税 | 2.60% | 15.0% × 17.3% |
| 合計税率 | 23.99% | 住民税均等割は含まず |
| 年間所得400万円~800万円まで | ||
|---|---|---|
| 税目 | 所得に対する税率 | 参考 |
| 法人税 | 15% |
|
| 復興特別法人税 | 1.5% | 15.0% × 10% |
| 事業税 | 4% | |
| 地方法人特別税 | 3.24% | 4% × 81% |
| 法人住民税 | 2.60% | 15.0% × 17.3% |
| 合計税率 | 26.34% | 住民税均等割は含まず |
法人の利益(所得)に対して課されてくる税率は、ざっくりと算定すれば上記の通りとなります。法人の年間所得が800万円までならば、23.99~26.34%の間で税額が算定されることとなります。
ざっくりと考える為に、平均である25%くらいの税率と考えると、
役員報酬に課される税率(所得税率 + 住民税率)が25%以下であれば、会社の利益を役員報酬として支出した方が節税のみを考える上で有利ということになります。
それでは、年収がいくら位までならば、税率25%以下となるのでしょうか。
所得税率は累進課税となっており、収入金額が大きくなる程、税率は上がってきます。
具体例で考えてみましょう。
税負担は、家族構成・社会保険の標準報酬月額・生命保険等の加入の有無により変動いたします。
標準的なモデルとして検討をしていきます。
家族構成:夫(35歳)、妻(35歳 所得¥0)、子供(5歳)
社会保険加入、生命保険料等の加入による所得控除は10万円
| 月収 | (1)年収 | (2)(所得税 + 住民税) | 税負担((1)÷(2)) |
|---|---|---|---|
| 500,000 | 6,000,000 | 455,300 | 7.58% |
| 1,000,000 | 12,000,000 | 2,007,300 | 16.72% |
| 1,500,000 | 18,000,000 | 4,359,300 | 24.21% |
| 2,000,000 | 24,000,000 | 6,909,000 | 28.78% |
| 2,500,000 | 30,000,000 | 9,759,000 | 32.53% |
上記は概算数値ですが、月収2,000,000円(年収24,000,000円)以上になると、税負担が25%を超えておりますので、月収1,500,000円程度の報酬であれば、会社で課税させるよりも、節税効果があることとなります。
上記概算では、妻を所得¥0として試算しておりますが、妻に事業を手伝ってもらえれば、給与を出すことで、所得を分散させることも検討できます。
税理士によるサポート事例
お問合せはこちら
Menu
インフォメーション
お問合せ・ご相談
お問合せはお電話・メールで受け付けています。
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
受付時間/定休日
受付時間
10:00~17:00
定休日
土曜日・日曜日・祝日
アクセス
〒162-0066
東京都新宿区市ヶ谷台町16-6
16ビル2階
都営新宿線「曙橋駅」 徒歩7分